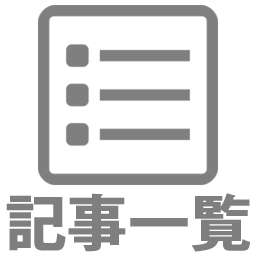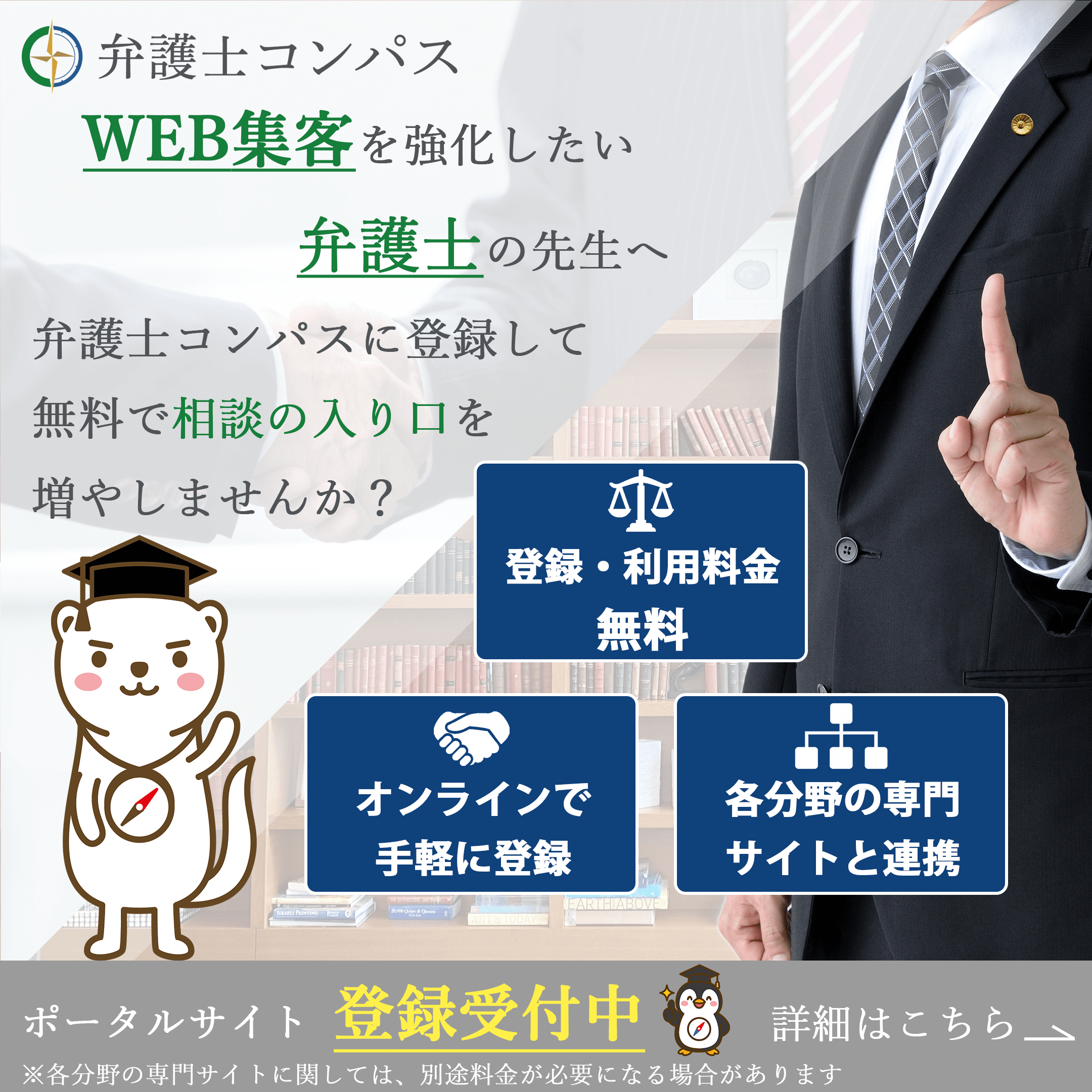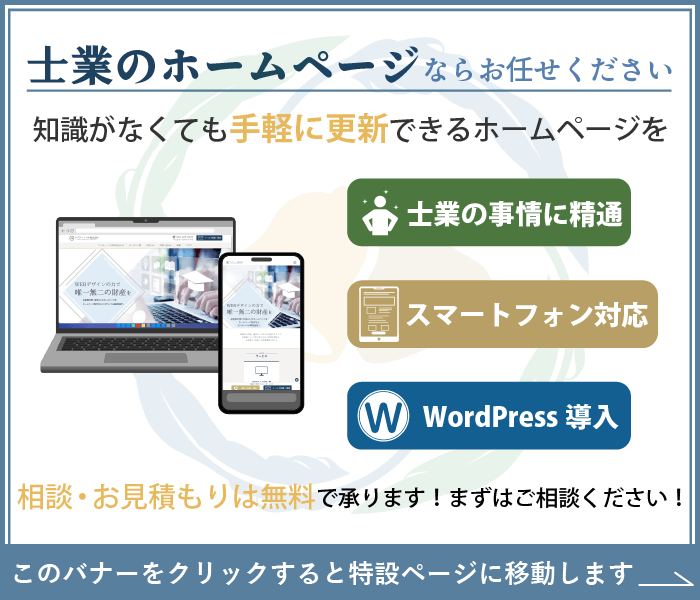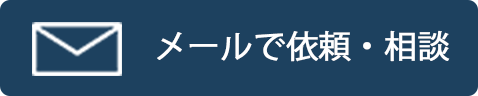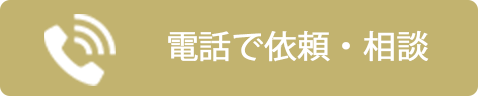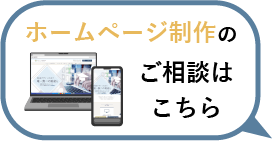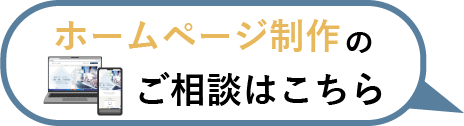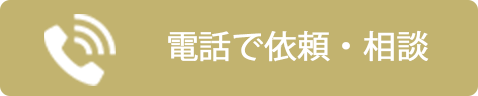-
集客・マーケティング2024年6月12日
非弁提携とは?3つの事例と弁護士が非弁提携に陥らないための対処法

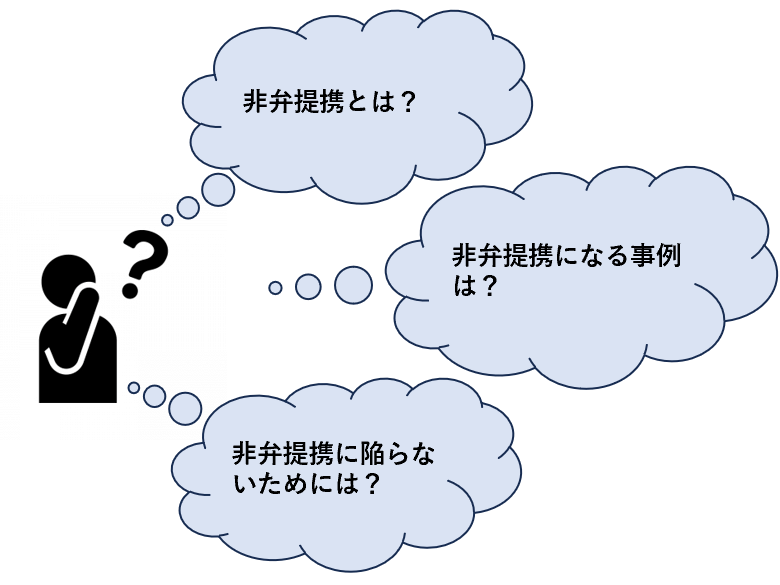
弁護士として業務をしていくなかで、非弁提携に巻き込まれてしまわないか不安に感じていませんか?
非弁提携を行うつもりはなくても、広告業者やコンサルなど気づかないうちに非弁に取り込まれてしまうこともあるという話を聞くこと心配になりますよね。
非弁提携とは、弁護士でないのに法律事務を行う非弁業者と弁護士が提携をすることです。
非弁提携については、弁護士法及び弁護士職務基本規程により禁止されています。
非弁提携の典型的な事例としては、名義貸し、報酬の分配、紹介料の支払いなどがあります。
非弁業者が弁護士を食い物にする手口として、独立直後に電話勧誘などがされたという話を聞くことが増えてきています。また、広告業者を装った営業がされたり、非弁業者の社員を事務所に派遣して乗っ取ってしまったりという話も耳にします。
非弁提携に陥らないためには、紹介料を払わず、弁護士業務は自分で行うという当たり前のことに注意したうえで、不安がある場合には知り合いの弁護士などに相談するということが大切です。
また、そもそも業者に頼らずに集客できるだけの力を身に着けておけば、非弁業者も付け入りにくくなります。
昨今、非弁提携がメディアで報道されるケースも生じており、社会的な関心が高まると同時に、問題も深刻化しています。
この記事をとおして、少しでも、弁護士が非弁業者に取り込まれてしまうことを防ぐことができれば幸いです。
今回は、非弁提携とは何かを説明したうえで、3つの事例と弁護士が非弁提携に陥らないための対処法を解説していきます。
具体的には、以下の流れで説明していきます。
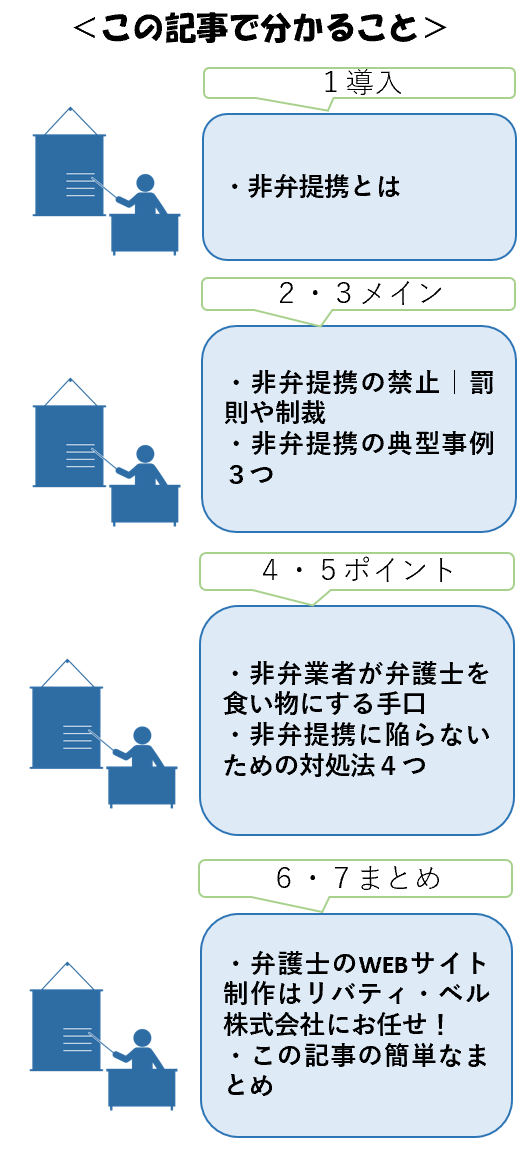
この記事を読めば、非弁提携に巻き込まれないためにどうすればいいのかがよくわかるはずです。
目次
1章 非弁提携とは
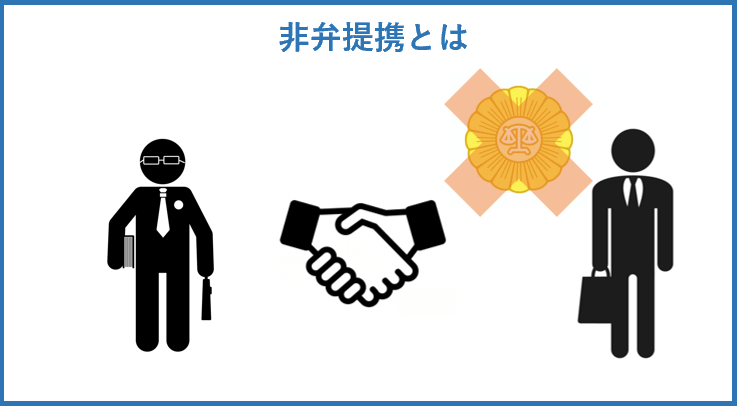
非弁提携とは、弁護士でないのに法律事務を行う非弁業者と弁護士が提携をすることです。
弁護士でない者は、法律事務を取り扱うことが禁止されています(弁護士法72条)。
高度の義務が課され、法的に十分な能力があることが担保された弁護士のみが法律事務を行うことできるとすることによって、依頼者の利益や法律秩序を守ろうとしているのです。
例えば、弁護士でない方が法律事務を行うことができると、誤った知識により依頼者に不利な対応をしたり、正確な見通しやリスクを説明できなかったりする可能性があります。
また、依頼者自身に不利益を与えない場合でも、法的な手続きを無視して、自力での権利救済が横行するなどの可能性も考えられます。
そして、弁護士がこのような非弁業者と提携する場合についても、同様の被害が発生したり、拡大したりする可能性があることになります。
そのため、弁護士が非弁業者と提携することは、「非弁提携」と呼ばれ規制されているのです。
2章 非弁提携の禁止|罰則や制裁
非弁提携については、弁護士法及び弁護士職務基本規程により禁止されています。
前記のとおり、非弁行為が行われる場合と同様、弁護士が非弁行為に加担した場合にも、依頼者の利益や法律秩序が害されることになるためです。
具体的には、禁止されている非弁提携を整理すると、規制されている行為には以下のものがあります。
弁護士法27条に違反した場合には刑罰があり、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されることになります(弁護士法77条)。
また、刑罰は課されなくても、弁護士法や弁護職務基本規程に違反した場合には、戒告や業務停止、退会命令、除名等の懲戒を受ける可能性があります(弁護士法56条、57条)。
3章 非弁提携の典型事例3つ
分かりやすいようによくある非弁提携の事例を紹介していきます。
例えば、非弁提携の典型事例としては、以下の3つを挙げることができます。

それでは、これらの事例について順番に説明していきます。
3-1 事例1:名義貸し
非弁提携の典型事例の1つ目は、名義貸しです。
例えば、非弁業者が、①法律事務所の名前を使って広告を運用して、大量に債務整理事件の受注を行い、②法律事務所に非弁業者の従業員を派遣して、これらの派遣された従業員が中心となって法律事務を含む事件処理を行っており、③弁護士が①②を是認していたような場合です。
とくに①と②が同じ業者である場合、又は、実態として同一の業者であると評価しうる場合が多いので注意しましょう。
3-2 事例2:報酬の分配
非弁提携の典型事例の2つ目は、報酬の分配です。
弁護士の売り上げの一定割合を業者に支払うと言った場合には、報酬分配の制限に反する可能性があります
例えば、弁護士が営業代行業者に対して、営業代行業者が受注した案件に係る報酬金の2割を払うといったような場合には、報酬の分配とされる可能性があるでしょう。
3-3 事例3:紹介料の支払い
非弁提携の典型事例の3つ目は、紹介料の支払いです。
例えば、不動産業者や隣接士業等から、事件を紹介された際に、お礼として10万円を支払うといったような場合などには、紹介料の支払いとして許されないことになります。
4章 非弁業者が弁護士を食い物にする手口
非弁業者は、あの手この手で弁護士を食い物にしようとしてきます。
一見して、非弁業者であるとはわからない態様により弁護士に言い寄ってくるのです。
例えば、非弁業者が弁護士を食い物にする手口としては以下の3つがあります。

それでは、各手口について順番に説明していきます。
4-1 手口1:独立直後の電話勧誘
非弁業者の手口の1つ目は、独立直後の電話勧誘です。
非弁業者は、あまり事件がなくて困っていそうな独立直後の弁護士を狙います。
例えば、独立した後、怪しい営業の電話がたくさんかかってくることになります。
突然、「弊社のクライアントの相談に継続的に乗っていただける先生を探しているんです」、「問い合わせが多すぎるので助けてください」、「先生は●●案件の相談の対応はできますか」などと言われることもあります。
不審な電話であることは明らかですが、集客に困っていると、このような話に耳を傾けてしまい、非弁スキームの中に取り込まれてしまうことになります。
4-2 手口2:広告業者を装った営業
非弁業者の手口の2つ目は、広告業者を装った営業です。
広告業者が、いきなり事務所に飛び込み営業がきたり、電話をかけてきたりすることがあります。
弁護士であっても広告を利用すること自体は、規程を守って行う限り問題ありません。
しかし、昨今では、広告業者と名乗るものの、実際にはサービスの内容が非弁提携となっていたり、料金体系に問題があるような業者も紛れ込んだりしています。
弁護士の広告規制については、以下の記事で詳しく解説しています。
4-3 手口3:非弁業者の社員の派遣
非弁業者の手口の3つ目は、非弁業者の社員の派遣です。
非弁業者の従業員を法律事務所に送り込まれ、事務所を乗っ取られてしまうケースが出てきています。
非弁業者の従業員が、法律事務所の処理等について指揮を執り、機械的に大量に処理を行い、弁護士が事件にほとんど関与しない状況とされてしまいます。
法律相談を弁護士資格のない者が行っているという事案も生じてきています。
5章 非弁提携に陥らないための対処法4つ
非弁提携に陥らないためには、非弁業者の手口を知ったうえで、常日頃から非弁行為に注意を払うことが大切です。
弁護士自身は非弁行為に加担するつもりはなくても、気を抜いているといつの間にか非弁業者に取り込まれてしまいます。
具体的には、非弁提携に陥らないための対処法としては、以下の4つです。

5-1 対処法1:紹介料や紹介歩合を支払わない
非弁提携に陥らないための対処法の1つ目は、紹介料や紹介歩合を支払わないことです。
紹介により案件を獲得するというのは、弁護士の伝統的な集客方法の1つです。
紹介料の支払いの禁止というのは、どの業界にも存在するものではありません。紹介料の支払い等が当然の慣行となっている業界もあります。
紹介してくれる方には、弁護士は紹介料の支払い等ができないことについて説明し理解を得る必要があります。
また、広告業者への料金の支払い等についても、紹介料や報酬の分配とされることがあるので注意が必要です。
広告業者への料金の支払いについては、問い合わせの件数に応じた報酬体系となっていないか、売り上げに応じた割合的な報酬体系となっていないか等を確認しましょう。
5-2 対処法2:広告業者から社員の派遣を受けない
非弁提携に陥らないための対処法の2つ目は、広告業者から社員の派遣を受けないことです。
昨今では、広告業者と同じ会社、又は、実態として同一の業者であると評価しうる会社が、事件処理を行う従業員を派遣するなどと言ってくるケースが出てきています。
広告を出すことで大量に案件が獲得できるため、それを処理する人員が必要であるなどと唆されるのです。
そうすると次第に集客から事件処理までのすべてを非弁業者が行っているといった状況になってきてしまいます。
案件を処理する人手が不足している場合には、法律事務所で新たに事務職員や弁護士を採用することが望ましいでしょう。
少なくとも、広告業者から従業員の派遣も受けることにはリスクがあります。
5-3 対処法3:怪しいと思ったら知り合いの弁護士に相談する
非弁提携に陥らないための対処法の3つ目は、怪しいと思ったら知り合いの弁護士に相談することです。
同期や先輩の弁護士、弁護士会の相談窓口などに相談すれば、客観的な視点からアドバイスをいただくことができます。
自分だけでは判断に悩む場合には、他の先生の意見も聞いてみることで、冷静に判断できることがあります。
5-4 対処法4:業者に頼らずに集客できる力を身に着ける
非弁提携に陥らないための対処法の4つ目は、業者に頼らずに集客できる力を身に着けることです。
非弁業者は、弁護士が集客に困っているということに付け込んできます。
弁護士の競争が激化して案件の獲得が簡単ではなくなったことから、新規の相談が中々来ないと悩んでいる先生の方も多いでしょう。
事務所経営に不安があり、いつまで経っても新規の案件が増えないと、徐々に冷静な心理状態ではなくなっていきます。
そのような状態で、広告業者やコンサル等を装った非弁業者から話を持ち掛けられると、藁にもすがる思いで契約を結んでしまうのです。
一方で、業者に頼らずに集客できる力が身についていれば、非弁業者の甘い言葉にも惑わされずに、冷静に判断することできます。
非弁業者からの電話も、「これ以上、案件について対応できないので結構です。」とだけ回答して会話が終了するので、甘い言葉を掛けられること自体もなくなっていきます。
このように業者に頼らずに集客できる力を身に着けることができれば、非弁業者に付け込まれる隙がなくなるのです。
6章 弁護士のWEBサイト制作はリバティ・ベル株式会社にお任せ!
リバティ・ベル株式会社は、弁護士が代表取締役を務める会社であり、弁護士のWEBサイト制作に力を入れています。
WEB制作業者はたくさんありますが、業者ごとに得意不得意があり、弁護士業界に精通している業者はごくわずかです。
リバティ・ベル株式会社では、法律事務所のホームページやオウンドメディアの運営について圧倒的な経験とノウハウを確立しています。
例えば、弁護士がホームページを制作するにあたっては、「品位を害するような記載はしたくない」、「解決事例を自分で更新できるようにしたい」、「料金表を簡単に更新したい」、「所属弁護士会は必ず書いて欲しい」などの要望があるはずです。私自身がそうでした。
是非、先生方が独立するにあたって法律事務所の財産となるホームページを制作させていただければ幸いです。
まずはオンライン(ZOOM)にて簡単に先生のご要望をおうかがいさせていただき、適切なサービスをご提案させていただきます。
お気軽にお問合せください。
料金表については、以下のページから確認いただくことができます。
WEBサイト制作料金表|リバティ・ベル株式会社7章 まとめ
以上のとおり、今回は、非弁提携とは何かを説明したうえで、3つの事例と弁護士が非弁提携に陥らないための対処法を解説しました。
この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。
この記事が非弁提携に悩んでいる弁護士の方の助けになれば幸いです。
以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。
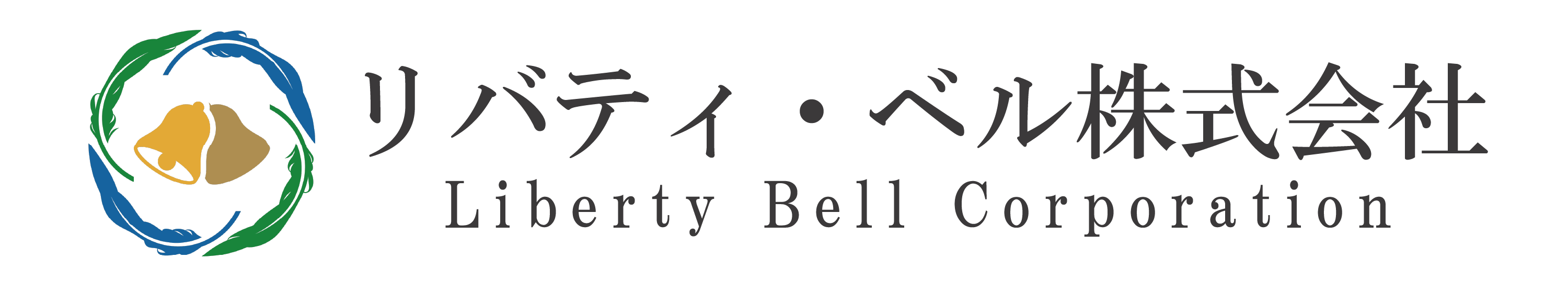

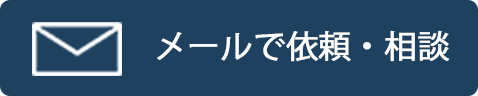
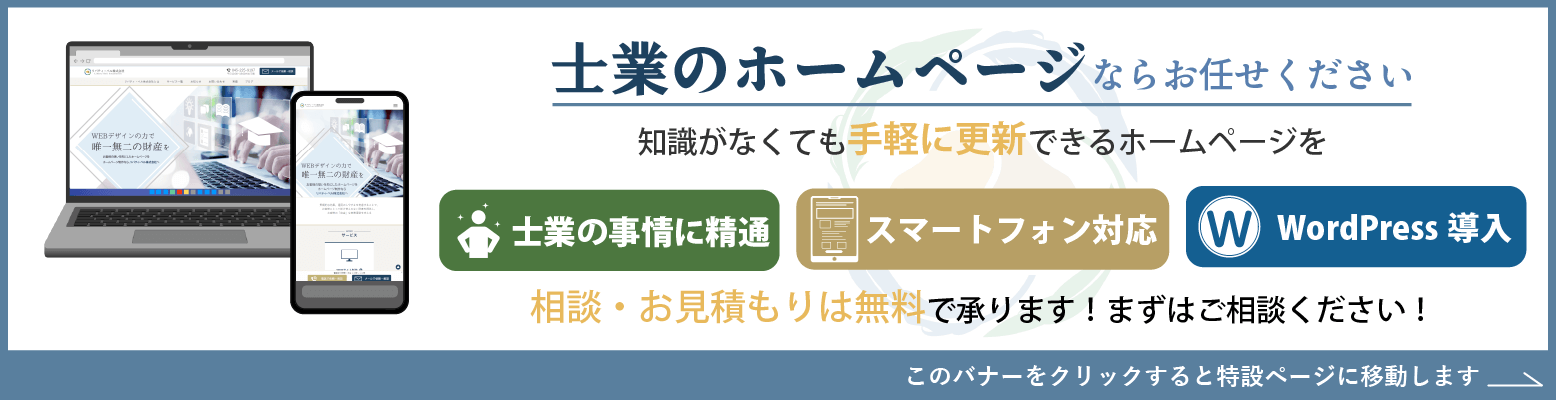
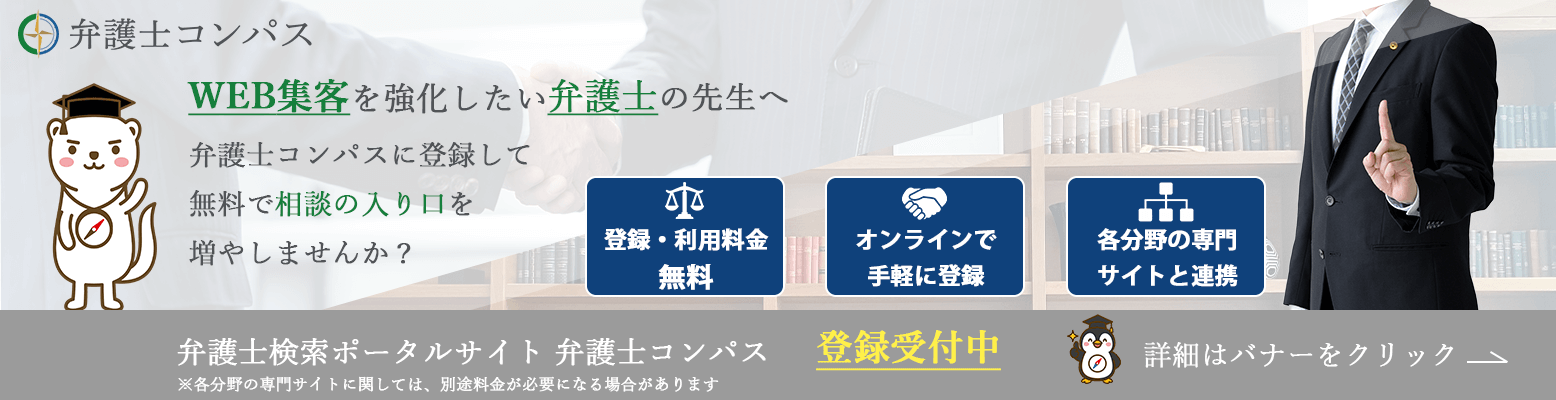


8つ!.png)